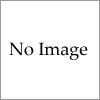
鈴木保奈美の水着カットがあるところが売りでしょう。
中古で購入する方は四つ折りのポスターが付いているか確認した方がいいでしょう。

ドラマには不倫、離婚、死などやや非日常的な展開がつきものです。そこに魅力的な主人公、華やかな舞台設定、美しい風景などをちりばめ見る側の関心を惹くように作られるのだと思います。この点、「恋人よ」は典型的なドラマとも思えます。その展開は尋常でなく激しいものです。結婚式場や新居での偶然な出会い、不倫の発覚、出産、離婚、闘病、そして主役の4人が再び心を通わせるラストまで「安心して」見られる場面はほとんどありません。予定調和のドラマを見慣れた私には、当初一見幸せな生活を棒に振った4人が痛々しく思え、後味の悪さを感じていました。
しかしさらなる幸せを将来に向け追い求める気持ち、対して過去をいとおしく思う気持ち、いわば心の焔は誰にでもある。状況によっては、本作のように胸騒ぎを覚え、一線を越えてしまいたい思いに衝き動かされることもあるのではないでしょうか。それぞれの感情表現が秀逸です。何度も見返した今は、当初思った痛々しい感じはしなくなり、自分の気持ちに忠実にあろうとして無理な行動に出ながらも、別れた人を最後まで思いやるような複雑で奥深い心の動きを、肯定的に捕らえたいと思っています。
鈴木保奈美が演じる愛永の心の焔が、周囲を巻き込み状況を一変させてしまう様には目を見張るものがあります。秘めた情熱を燃え上がらせたものの、愛する人に理解されず、重い病気にもなり、彼女は深い孤独に陥ります。しかし、その後彼女がかけがえのない人であると気づいた者たちは恩讐を越えて、彼女の余生を最高のものにしようと再度集まります。
映像とセリフの放つ強い説得力は、見るものの関心を惹こうと細工された「ドラマ」のレベルではありません。三浦半島や沖縄の美しい映像をバックに、役者としてピークの時期に撮影された主役4人の充実した演技を味わうことのできる秀作です。

「月9」という言葉はこのドラマで始まったといえるでしょう。そして、「最初」にして「最高」。
脚本の坂元裕二は、「リカ」と「さとみ」の色づけを柴門ふみの原作とは逆方向にアレンジし、結果として奏功しました。またトレンディ・ドラマの路線をしっかり維持しながら、ファンの求める結末とは逆方向となる原作のシナリオ展開は、その後の「アンチ・ハッピーエンド」なドラマがしばらく続くきっかけにもなりましたね。
俳優陣では、鈴木保奈美が溌剌とした演技で輝き、当時はまだ無名と言ってよかった織田裕二が一気に「織田スタイル」を確立し、江口洋介・中山秀征・西岡徳馬等の俳優が脇をしっかり固めた、非常に安定感のあるドラマでありました。
また、主題歌(小田和正)も良いのですが、劇中のBGMを担当した日向敏文の音楽も秀逸で、「リカのテーマ」をはじめとする劇中曲はそれだけで聴く価値があるといえましょう。
結局、原作・脚本・演出(ミスタートレンディドラマの永山耕三)・俳優陣・音楽のすべてが優れていると大傑作ドラマが生まれるというお手本のような作品だったと思います。
またいつか、このようなドラマが作られることを願いつつ、星5つの評価といたします。
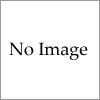
この作品は非常に難解なドラマであると個人的に思っている。
それには大きく2つの理由がある
1、心理テストの答え
作中にたびたび登場する心理テストがある。
「この世に自分ひとりになって、船で逃げなければならない。
次の動物を一匹だけえらんで連れていける。どれを選びますか?」というテストである。
メインキャストのほとんどが羊(つまり一番必要としているのは愛)と答える。しかしシロは船に乗らないと答えた。
最初はまりあも「それじゃテストにならないじゃん」などと言いシロの答えを一蹴するが最終話ではまりあもこの答を選んでいる。船に乗らないとは何を意味するのか、いまいち分からない。
2、この世の果てとは?
本作の題となっている『この世の果て』
個人的にはこの意味も理解に苦しむ。
前述したことにも関係するが、「この世に自分ひとりに・・・」
の心理テストでは自分は『この世の果て』に行くことができる。(自分以外の人間がいない世界に行くことができるからその時に何を連れて行くのかによって『この世の果て』に何があるのかが見えてくるのではなかろうか。
つまり羊=愛
孔雀=金
馬=仕事
虎=プライド
私の論理によると彼ら(まりあとシロ)は何も連れていかないわけであるから『この世の果て』には何も無いことになってしまう。
だが作品を見ている限りではそこには愛があると解釈できる。
しかも佐々木実が自分を破たんさせたルミを見つけたときに「彼女をこの世の果てに連れて行く」と言っていたことも
私が混乱している理由である。
このように本作は非常に抽象性が高い。(私のミスリードあるいは考えすぎかもしれないが)
私は恥ずかしながらまだ10代であり、愛というものをよくわかっていない。
だが本作は「愛とは?」という問いに対して、ヒントを与えてくれている。
私は時あるごとにこの作品を再見して、一生見続けていくことになるだろう。
| 