
本書のタイトルの「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ」はバンド名のそれではなくて彼らのファーストアルバムのタイトル、の事なんですね。
1冊まるごとあの名盤に関する様々な「ネタ」が次から次へと。あのアルバムが大好きな方でしたら大変興味深く、興奮してスルスル読み進めてしまうはず。
ROCKトリヴィアも満載なのでヴェルヴェットにさほど興味が無い人でも楽しめると思います。
中でもアンディ・ウォーホルとジョナサン・リッチマンが再会した時の話がナイス。
その時のウォーホルの素敵過ぎる言動、いつかマネしてみたいなと思いました。
カヴァーを取り外した中の表紙のデザインもイカしてました。まさにPEEL SLOWLY AND SEE!
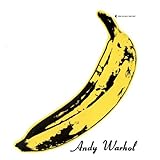
ベルベッツの1stで67年の作品。当時は考えられなかったノイズや不協和音を鳴らすパフォーマンスや、ドラッグやSMについて歌うという全く新しい手法で登場したアルバム。発表された当時はチャートの100位にも入らなかったみたいです。その音楽に対する姿勢は今でも多大な影響力を及ぼしてます。パンク、オルタナの始祖じゃないでしょうか。または元祖シューゲイザー。あのアンディ・ウォーホルが手掛けたジャケットもいい感じじゃないですか。

私が最初にこの手の音楽やアートに目覚めたのは、約50年前の中学・高校時代。それからというものは、連日連夜ロックや現代アート三昧。
当時は今のような海外アーティストのビジュアル媒体は少なく、ひたすら輸入レコード店で入手したレコードそのものが重要な情報源であった。
久しぶりにこのDVDを見ると、当時の思いがふつふつとわきあがってきた。
演奏も聞き手側の私も、年を経るにしたがって感性が若干ちがっては来ているが、根本的には同じ方向を向いていたことに安心した。
今やニコもウォーホルも黄泉の国に旅立っていて、幾ばくかの寂しさを覚えたものの、オリジナルメンバーが顔を揃え、ひたすら演奏に打ち込む姿がしばらく脳裏を離れなかった。
そして、モーリン・タッカーのバスドラムのテクニックが、脚ではなく腕によるものであることにちょっと意外性と安堵感を覚えた。
※リージョンエラーが出るのではと心配していたが、それもなくてよかった。

ジョン・ケール脱退後のヴェルヴェッツはつまらないというご意見をお見かけするが、このバンドの核は紛れもなくルー・リードであり、ジョン脱退以降も、ヴェルヴェッツは、ポップス史上に確かな業績を残してきたと断言したい。緊張感や実験性に満ちたファーストやセカンドアルバムと比べるとこのサード・アルバムは、一聴すると、いかにも分が悪いように思われるが、他のアルバムでは、表現しきれなかった、叙情性、繊細さなどの魅力を提示することに成功している。
それと、ジョンが、実験精神に富んでいたことは、事実であるが、ルーもジョンほどではないにしろ、実験精神や音楽的野心は、強く持っていたことも、誤解がないよう述べておきたい。それは、本アルバム収録の「Murder Mystery 」や、ソロ期のアルバム「Metal Machine Music」を、考えていただければ、ご納得いただけると思う。ただ、ルーには、ジョンと比べると、実験的アイディアを作品に昇華する能力が劣っていたことも、「Murder Mystery 」や「Metal Machine Music」で証明されているように思う。なので、ジョンのいないヴェルヴェッツに物足りなさを感じる諸兄もおられるであろうことは理解出来るし、最終的には、好みの問題ということになってくるのであろう。
話は逸れたが、このサード・アルバムである。名曲満載である。とりわけ、触れると壊れてしまいそうなな、繊細さ、脆さを感じる「Candy Says 」「Pale Blue Eyes 」「Jesus」に心を奪われると同時に、セカンド・アルバムからの振幅の激しさに驚かされるところである。こういった楽曲は、ややもすれば、言葉は悪いが、女々しくなり過ぎるきらいがあるが、ここに収録されている楽曲は、そうはならず、何か強い芯のようなものが通っているところが、非凡に思う。
この、「何か強い芯のようなもの」を自分なりに考察してみたのだが、ルーのパーソナリティによるところが一番大きいのかもしれない。ルーは傷つき易い感性の持ち主でもあるが、激しく自己主張するエゴの持ち主でもあり、非常に弱い部分と非常に強い部分が同居している複雑な人物である。また、彼は都会人特有のクールな視点を持っており、詩人としての優れた観察眼、いわば一種の客観性を有した人物でもある。このような、ルーのパーソナリティを反映した楽曲は、弱い自分を曝け出しつつも、そんな心の裏側に隠れる人間のしたたたかさを覗かせ、優しさの中にもどこかクールな感触を与えるのではないだろうか。そこには、なにか普遍的な輝きが感じられる。
「何か強い芯のようなもの」を感じる理由に、もう一つ考えられるのが、ルーをはじめ、メンバー全員のロックン・ロールに対する信念にあるように思う。ブルースを源流とする、この土着性を内包した力強い音楽、アイク・ターナー、チャック・ベリー、ボ・ディドレーと言った偉大な先人が、作り上げてきた聴くものの心を躍動させずにはおれない、パワーを持った音楽、ロックンロールへの揺ぎ無い信頼感が、そして、自分達は、何があってもロックンロールを演るんだという信念が、このアルバムの根底に貫かれているからこそ、このアルバムがみっともない単なる自己吐露の自慰行為的なものに落ちなかったのではないだろうか。
以上長々と、偉そうに拙文をたらたらと書き綴ってすいませんでした。何が言いたいかというとサードアルバムも名盤なので、是非聴いてみてください、ということです。「What Goes On」最高ですよ。浮遊感に満ちたキーボードの調べと心地よいギターストロークが延々と鳴り響くアウトロは、このまま永遠に聴いていたいと思うほどです。

私が最初にこの手の音楽やアートに目覚めたのは、約50年前の中学・高校時代。それからというものは、連日連夜ロックや現代アート三昧。
当時は今のような海外アーティストのビジュアル媒体は少なく、ひたすら輸入レコード店で入手したレコードそのものが重要な情報源であった。
久しぶりにこのDVDを見ると、当時の思いがふつふつとわきあがってきた。
演奏も聞き手側の私も、年を経るにしたがって感性が若干ちがっては来ているが、根本的には同じ方向を向いていたことに安心した。
今やニコもウォーホルも黄泉の国に旅立っていて、幾ばくかの寂しさを覚えたものの、オリジナルメンバーが顔を揃え、ひたすら演奏に打ち込む姿がしばらく脳裏を離れなかった。
そして、モーリン・タッカーのバスドラムのテクニックが、脚ではなく腕によるものであることにちょっと意外性と安堵感を覚えた。
※リージョンエラーが出るのではと心配していたが、それもなくてよかった。
|