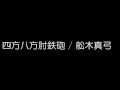内田吐夢監督+中村錦之助(萬屋錦之介)主演の東映版「
宮本武蔵」5部作(1961年〜65年)の第4部(1964年制作公開)です。
言うまでもなくこの5部作は、1958年を境に日本映画の観客動員数がピークアウトしてその凋落傾向が決定的になった時期と重なるにも関わらず、主演の錦之助の成長に合わせて一年一作の原則を堅持しながら作り上げられた豪華編です。「
宮本武蔵」は、東宝の三船敏郎版3部作(1954〜56年)、松竹の高橋英樹版(1973年)の他、テレビでも何度も映像化されてきていますが、その中にあってこれが決定版であるとの評価は、すでに定まっております。
5部作中、第1部は、武蔵(タケゾウ)から武蔵(ムサシ)へと変わる経緯が描かれる序章。最後の第5部(巌流島の決斗)は、定番の佐々木小次郎との対決で、いわば観客へのサービス編。第2部(
般若坂の決斗)から第3部(二刀流開眼)を挟んで第4部(一乗寺の決斗)までが、5部作の軸となる「名門吉岡道場vs.
宮本武蔵」のドラマです。
おそらく吐夢監督は、
宮本武蔵なる人物の成長よりも、名門吉岡道場の滅亡の悲劇に、より力点を置きたかったのでしょうから、この第4部は、まさにドラマのクライマックス編とも云えるでしょう。本来ならば、以前発売された高額のBOXを購入し、全5部をまとめて鑑賞するのが望ましいですが、第4部だけを見ても、この連作の真髄は十分に味わえると自信を持って言えるゆえんです。
この映画の一番の見どころは、もちろん、「一乗寺下がり松」と云う何の変哲もない田園に囲まれた大きな一本松の周囲で、最後の約20分間にわたって繰り広げられる、吉岡一門73人と武蔵1人の対決シーンです。その場面になると色が消える(カラーから白黒に変わるというよりも、文字通り、「色が消える」と云った方がふさわしいような、不思議な画調)ことでもよく知られていますが、特に印象に残るのが、二刀流の武蔵が、息づかいも粗く、ズボッズボッと薄氷の張った田んぼに足を取られながら相手を一人ひとり斬り伏せていく映像にかぶり、小鳥のさえずりが微かに聞こえるところです。夜明け前から日の出にかけての時間経過の中で、鳥たちも眠りからさめてきたんでしょうが、冷静に考えればどうでもいいような意地の張り合いで殺し合っている人間どもを尻目に、大自然は何も変わらず日々の営みを始めていきます。人間の卑小さ・矮小さをこれほど鮮やかに切り取った映像&音響には、なかなかお目にかかることはありません。
とにかく、くだらん意地を張る奴ほど、迷惑な存在はありませんからね。巻き込まれたりしたら、堪ったもんじゃない。戦中に書かれた吉川英治の原作と比べて、この5部作が、
宮本武蔵と云う人物に対して、実はかなり突き放した視点を持っているのも、日本敗戦後の中国で、8年間も過酷な抑留生活を体験し、意地の張り合い・殺し合いのバカらしさをいやというほど見てきた内田吐夢ならではの意図なのでしょう。
後年、「シン・レッド・ライン」を見た時に、「一乗寺の決斗」が数秒間の音響で表現したことを、こちらでは3時間もかけてやっているんだなあと、あの冗長でいささか狙い過ぎの映像を見ながら感じたものです。つい最近、「悪の法則」と「コズモポリス」を見て、「自業自得」、「足るを知る者は富む」の一言で済む話を、何をダラダラと人生訓の披瀝や哲学問答を続けているんだろうかと実にバカバカしく感じましたが、あれらも同様です。何事も、ダラダラ勿体付けて大袈裟にやればいいってもんじゃない。「寸鉄人を刺す」と云う言葉もありますしね。