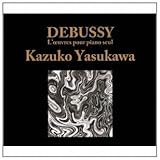
ドビュッシーの生誕150年企画CDであります。
しかも、安川加壽子氏の4枚組のCDでもあります。
CD4枚をすべてを聴いた感想は、
本当に「洗練」された演奏でありました。
1つ1つの音が絡め合って、
「洗練された」うねりになっています。
1969年から1971年にかけて録音された演奏ですが、
ドビュッシーのピアノ独奏曲が輝いています。
安川加壽子氏の研鑽に研鑽を積んだ演奏だからでしょう。
演奏家の演奏原理(哲学)を感じます。
このCDを聴いて、
コンサートで生の演奏を聴きたくなったのが本音です。
購入して本当によかった。

指導方法がひとつひとつ明確にしてあり、私が子供の頃よりも、練習本として進化している。ある程度弾ける人ならば、自分の子供を指導するのに、とても助かると思う。また、自分の復習にも。

私が幼稚園児だったころ(今から30数年前)からあった教則本です。
ほかの方も書いておられるように、中身は主にフランスやイギリスに伝わる民謡がメインです。
ちなみに音大系の小学校ではバイエルがメインですので、そういった学校にお子様を入れられる予定の親御さんは、バイエルを買われたほうがよろしいかと思います。

たまたまサンサーンスのピアノ協奏曲全集が出たので,楽しんでいたが,ふと気になった.私たちにこういう面白い音楽があることを教えてくれたあのピアニストのことを,世間は今でも覚えているだろうか.夢のような,美しい音楽と裏腹に,無愛想な言葉でしか話せなかったあのピアニストを.そこで日本語 Wikipediaで調べたら,この本がある,と教えて貰えた.それっとばかりに入手して,あまりの面白さに一気読み.ああそうだったのか.フランス語が母語だったのか.折角仕上げに入る時期に戦争に翻弄されて,母語からも先生からも切り離されて地獄同然のこの国に連れ出され,そのままここに住むのが運命だったのか.あまりの残酷さに声も出ない.この国は思い込みの強い連中ばかりが威張っているから,フランスの価値観からすればあり得ない常識がまかり通る.いじめが横行する.辛かっただろうな.でも,縁あってこの著者のような優れた人達が弟子として見ていてくれた.その回想の力たるや物凄いもので,今は亡き人がかつて奏でた音までも聞こえて来る感じがする. 昔,安川さんのファンであった者として,著者にお礼を申し上げたい.この本は古くはならないだろう.クラシックファンに強く推薦.

戦前、幼い時からフランスでピアノを学び、太平洋戦争直前に帰国、戦後のピアノの演奏活動で中心的役割を果たすとともに芸大での教育でも偉大な存在であった安川加壽子の評伝。
その門下生であった著者は、加壽子の奏法が意外とアルゲリッチに近かったとして、こう書く、「二人とも、一見鍵盤の上に無造作に手をのせているようにみえるのだが、その下から驚異的なスピードで音がつむぎだされていく。とくに手を交差させる部分では、左手に放物線を描くようにして、右手をのりこえ、魔法のようにしなやかに動きまわる。・・・どんな細かいパッセージも指だけで弾かれることはなく、必ず手首や腕が連動しているので、音にうるおいと輝きがある。前腕のすばやい交替で弾くトレモロ、ひじから勢いよくうちおろす切れのよいスタッカートも、加壽子のピアニズムがアルゲリッチと同じ伝統を受けついでいることを示している」と(p.265)。
加壽子は、ショパン(1831年、パリ着)、ドビュッシー(1872年、パリ音楽院)、コルトー(1917年、パリ音楽院教授就任)、レビィ(1920年、パリ音楽院教授就任、加壽子の直接の師)の伝統を受けつぐフランス式の奏法を学び、それをたずさえて1939年に帰国、19歳にして楽壇に鮮烈にデビュー。戦中も演奏を続けるが、フランスから持ってきたグランドピアノを空襲で消失し、ピアニストを諦めかけたが、戦後、見事に復活。ショパン、ドビュシー、ラベルの曲を天才肌の抜群のテクニックを基礎に、たおやかに優雅なピアニズムを信条とした。
一時、批評家からかなり手厳しいバッシングに似た酷評を受けた時期があったが、めげることなくかなりの高齢まで現役の演奏家として活躍し、多くの後継者を育て、また内外のコンクールの審査員として重責を果たした。
晩年、リュウマチを発症してからは、痛々しいかぎりだが、著者はその部分もきっちり書き込んでいる。
著者は、最後に結論のように書いている、わが国の音楽界は多くのピアノの演奏家を輩出しているが、何かが足りない、それは「音色、とくに弱音の魅力。作品の歴史的・文化的背景の理解をふまえた端正な様式感、古きよき時代を髣髴とさせる馥郁たる香り、演奏の芸術性と運動の合理性。それらの絶妙なバランス。つまり加壽子にあって日本の若手にないもの。他のどの点をいかに完璧に満たしても、どうしても満たし切れなかったもの」(p.317)である、と。この結論部分は、ややテンションが高く、加壽子を真に理解しえなかった日本の音楽界に対する著者の苛立ち、無念さが文章のバランスを危うくしているほどである。加壽子の音楽性への傾倒のゆえであろうか。
| 