
牧野氏なのに、時代小説で青春小説だった
猟奇的な連続殺人事件といった牧野氏らしい要素があり、
それが各章を貫くメインのストーリーとなっている
しかし、大正時代の美術専門学校に通う4人の女性が各章の主人公となっており、
彼女達の青春のひとときの方が本当のメインのように感じた
芸術論や格闘シーン等、色々な要素があり、最後まで楽しく読めました
今までに読んだ著者の作品のなかで、一番好きな作品でした

遂に完結!!!
あいかわらず、女性同士の壮絶な異能力バトルが繰り広げられる
そのかわり、男性(ゾンビ)は存在感が物凄い薄い
ただ、なぜ女性は「医療虫」の暴走でこのような様々な異能力が発現するのか理論的な説明がない
SF好きとしては少し残念だった
また、能力があまりにも物理法則を超越しすぎている気も
テンションの高いバトルシーンはめちゃめちゃ面白かった
異能力バトルものとしては小林泰三著「人造救世主」シリーズもあります
こちらは、能力が物理法則内に収まっています
そういう点では良かったです
ただし、文章があまりにも客観的というか解説ぽい感じで面白みには少し欠ける点もありました
この2作品を足して割ったら、個人的にはめちゃくちゃ好みな作品になりそうだ
今回はあとがきが付いていなかった
それも残念でした
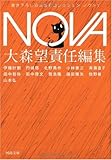
11編中、
「お、なかなかおもしろいなあ。この作家の他の作品も読みたいなあ」
と思ったのが5編、
「ん〜、波長が合わないなあ。読むのに忍耐を要したなあ」
と思ったのが4編(うち2編は長い!)、
でした。
第2巻も出るようですが、少し待って古本で安く買ったほうが無難かな。

すばらしく直截的なタイトル/ジャケットがストレートなホラーっぷりを想像させる、牧野修久々の角川ホラー文庫書き下ろし作。
その顔を見た者は必ず、死ぬ!
という身も蓋もないキャッチはほとんど失笑ものだが、直訳すればそーゆー話。死へ向かうそのプロセスや原理に取り立てた斬新さは無いが、あぁなんだかヤなものに苛まれているなぁという「恐怖」の感覚、精神的な病理の感覚は、読み進むほど確実にその嵩(かさ)を増す。
不可解な言動を最後に自殺した大学教授の息子/高橋は、その遺品を整理する中で三冊のノートを見つける。高橋はそこに記された父の手稿を読むことで、自死へ至った父親の内心を探り始める。物語はその日記の断片と、高橋の周囲で相次ぐ異常な死の連鎖を並行させて進んでいく。そしてやがて、その鎖の手元を握る存在が浮かび上がり、物語は終局へと進んでいく。
馬鹿にされ嘲笑われコケにされ罵倒され虐められあるいは大事な存在を喪失させられそのココロに大きなダメージを負った人間が、タールのようにどす黒く鬱積したエネルギーをぐるりとネジれさせ外部へ他者へと向けていく過程の禍々しさ痛々しさ狂おしい怖さを描くことにかけては超一級である牧野修の「徴(しるし)」は本作でも各所に刻印されていて、そのイタさコワさカナしさの鮮烈がイヤが上にも強烈に胸をエグる。あぁいやだいやだ見たくないよぉおと思いつつも目が離せない「壊れてしまった」人たちの言動は、生理的な方面からの恐怖を煽る。
あとがきにて作者は「ただ出てくるだけの幽霊なんて怖くない」と書いている。そして「いろいろ考えている間に、とうとう私はその解答を思いついてしまったのだ。幽霊の正体と、だからこそ幽霊は災厄をもたらすのだとういう、その解答がこの小説の核になっている」と。
牧野修が生み出した人間に"物理的に作用する"それと、それを引き起こすための"カギ"には、うそだうそだと解っていながらも夜中に思わずゾッとしてしまうような。たとえば「リアルヘヴンへようこそ」のようなトンだ幻想大作ではないし、「死せるイサクを糧にして」のような徹底した不条理とも違うが、牧野修のイヤ巧さが巧妙に張り巡らされた良作だったと思う。ラストにかけての、旧き良きアメリカンホラーを思わせるドタバタとホロり加減もグッド!

情報が急激に広がる時には、そこに、広い分野に散らばる数多くの人々と浅くつながる少数のキーパーソンが存在する。
今、社会学や経済学の分野で最も注目を浴びるこの理論を、「もし、そのキーパーソンが悪意を秘めていたら?」と仮定して展開したホラーミステリーです。
三人称一視点でもなく、神の視点でもなく、三人称で視点が唐突に入れ替わる記載法を取っているため、読み始めは混乱することと思います。
作家は元々不安定な筆力の人ではなく、おそらく今回の視点の混乱は意図的に設計されたものと思われます。結果、非常に不安な雰囲気を作成するのに役立つ他に、登場人物の内面を掘り下げる効果が得られています。
牧野さんは、個性的な人物造形にすぐれた作家ですが、その造形があまりに特殊であったため、今までの作品では、人物に感情移入しづらいという欠点がありました。
今回、人物の強烈な個性はそのままに、その心理が深く掘り下げられたため、各々の人物の異様な行動原理が、普通の人間にも納得のいく形で提示されています。とうてい理解しがたい人物が、奇妙なことに理解できるのです。
そうして立ち現れた個性的な人々が、各話毎に一人、表舞台から惜しげもなく消されていきます。もったいないというか、贅沢というか。
ことに、死んだ人物の幻を見る女性刑事が、その幻をけっして幽霊とは呼ばず死者と呼び、「死者には生前の時よりも二歩ほど親しみを感じて近づいていく」という描写の素晴らしさには、みぶるいしました。
けっして似た人物のいないだろう女性。だが、彼女のすさまじい孤独がまるで自分の物のように感じられて。
まさに、個性の陳列箱。どこまで手数があるのかと、ほんとうに感心しました。
| 
