
Merry Christmas Mr. Lawrence - The Criterion Collection (戦場のメリークリスマス クライテリオン版 Blu-ray 北米版)
先日高校の授業で「日本史に関係のある映画で何が見たい?」と協議したら、意外にもこの『戦場のメリークリスマス』が第1位になったクラスがありました。思えば坂本龍一の楽曲は邦画のテーマソングの中で今日最も良く知られたもの、ということになるのかも知れません。彼らの映画の感想も非常に面白いものでした。何よりこの映画から「痛み」を共有し、戦争というものをリアルに感じたようです。平成生まれすらいる彼らをしてそう感じさせた訳ですから、この映画が時代を越えて訴える力を持った傑作であるということを再認識させられました。
この映画の核の1つにセリアズの回想の部分があります(そしてこれは従来の大島渚なら決して撮ることのなかった映像です)。美しいこの映画の中でもこの部分は一際美しく、そして収容所のシーン以上に見ていて辛くなるものがあります。一方でヨノイもまた二・二六事件の現場に立ち会えなかったという悔恨を抱えており、その意味で2人はともに救済とも言うべき「死」へとストイックに進んで行かなくてはならない業を背負っています。かたや弟に対する「罪」の意識から。かたや同志に対する「恥」の意識から。 この映画は全編を通してこの「罪と恥」というテーマに真っ正面から取り組んでいます。しかしこの映画がドラマティックなのは、最後にそのような対立を超えて、お互いの心が通じ合う所にあります。それは「共感と寛容・慈愛」とでも言うべきものでしょうか。まさに「ファーデル・クリスマス」がつないだ文化と心の架け橋です。死を目前にしたセリアズの髪を持ち去るヨノイ、エンディングのたけしの笑顔にみんな心奪われるのですが、対立の果てに辿り着いた心の通い合いを何となく感じるからこそ感動できるのでしょう。そしてそれは現代の高校生にも十分すぎるほどにアピールする力を持っている訳です。大傑作です。もっと多くの人に見て欲しいです。 
戦場のメリー・クリスマス
あまりにも有名なテーマ曲。この曲を弾くためにピアノを習った。当時の教授はまだテクノなのでシンセの曲なんだけど、それが雪じゃなくて、熱帯の雨のような感じがしてなりません。でも個人的には2分弱のthe seedが一番泣けるかと…。
セリアズはその死によってヨノイの心に種を植えたんだと、あらためて感じる。 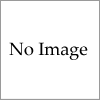
戦場のメリークリスマス [VHS]
16歳の時に初めて観てから、
数年おきにレンタルして観ていましたが、DVD導入を機会に買いました。 戦争、宗教、友情、家族、支配するものとされるもの。 そして「愛」。 最後の「メリークリスマス!ミスターローレンス!!」のセリフを残した たけしの笑顔は最高です。 
戦場のメリークリスマス―影の獄にて 映画版
主人公のイギリス人が第二次大戦で日本と密接にかかわることになり・・・というお話。
ここで描かれる日本人のキャラクターが著者が実際に関わった実在する人物か創作されたものかは判りませんが、日本人の本質を見事に射抜いているように感じました。その残虐でありながら美徳も持ち合わせ、冷酷でありながら礼節を弁えるという古くからある日本人の本質を捉えていて鋭い洞察に驚きます。 ここで著者は多分、反戦や厭戦の立場でこの小説を書こうとしたのではなく、戦争という極限状況で人間がどうあるべきかを問いつつ戦争の本質を探ろうとしたのではないかと思いましたがどうでしょうか。戦争の小説ですが、あまり戦闘シーンはなく殆どの場面が登場人物の内面の葛藤を軸に話が進むのでそういう風に思ったのですが・・・。 「戦場のメリークリスマス」の題名で映画化された作品に関して監督の大島渚氏は生前、日本の戦争映画に敵が描かれていないものが多くてそれが不満で撮ったと申してらっしゃいましたが、確かにこの原作を読むとこの当時の敵に当たる英米の人や連合国側の人間性がよく描かれていて感心させられます。このあたりに大島監督の琴線に触れたのかなとか思いました。 ピエール・ショアンドェルフェルの「さらば大様」等日本以外の人が日本について書いた戦争小説の系譜があるようですが、これもその系譜に連なる傑作だと思います。機会があったらご一読を。 
戦場のメリークリスマス [VHS]
この「戦場のメリークリスマス」は私が中学生の時にみた記憶がある。当時は坂本龍一の音楽への関心から足を映画館に運んだのだが、熱帯の重たい空気感とフィルムの色彩、音楽の美しさが印象的であった。ほぼ20年経過した今、改めて観直してみたが、多分に今日的な主題を持つ映画であると感じた。
本作は太平洋戦争末期における熱帯の島の捕虜収容所という閉鎖的な環境が舞台だが、そこでは過酷な戦争という環境において異なる文化的価値観(例えば、西洋と日本、キリスト教と国家神道、それらを背景としたセリアズの「罪」の意識とヨノイの「恥」の意識)を持った人々との対峙と葛藤が描かれている。この映画が優れているのは、その音楽や映像の美しさに加え、悲しい結果にもかかわらず異文化への理解を予感させるエンディングとなっている点であり、それを男女の愛情という月並みな枠組みに落とし込むのでなく、「文化の異質さと受容そのもの」を純粋に浮上させんがために、逆説的に戦争という価値観がぶつかりあうリアルな場とホモセクシャルな同性同士の交流が選択されたのではないかとさえ思える。この互いが異なる文化に立脚していても、それでも理解と受容は可能なのだというテーマはまさに今日的だ。 現在、日本では太平洋戦争時の映画が数多く制作されるようになっているが、同様に戦時中が舞台となっている「戦場のメリークリスマス」との質や内容の隔たりはどうであろう。昨今の戦争映画にお決まりの「愛するモノの為に死す」という構図の陳腐さについてはコメントしようもないが、問題なのはそういった構図の映画を受容する現在の日本の文化状況だ。その傾向に不安を感じるのは私だけではないだろう。おそらく現在、必要なのは「同質の文化」の称揚ではなく、まさに、本作「戦場のメリークリスマス」で描かれているような「異なる文化」へのまなざしと受容であるというのに。 |

|
戦場のメリークリスマス ED - Merry Christmas Mr. Lawrence Ending1983 Nagisa Oshima film. The scene of the movie last. Appearance: Tom Conti, Beat Takeshi (Takeshi Kitano). Composition / Arrangement / Performance by Ryuich... |
|
「戦場のメリークリスマス」についてなんですが、始めの方でデヴィット・ボウイは ... 戦場のメリークリスマス 『戦場のメリークリスマス』のあらすじを教えて下さい。 戦場のメリークリスマス [ デヴィッド・ボウイ ] ヤマハミュージックメディア 譜めくりの少ない!ピアノピース 戦場のメリークリスマス 【RCP】 坂本龍一/戦場のメリークリスマス/原曲を探しています。 "戦場のメリークリスマス"の着メロ 戦場のメリークリスマス 戦場のメリークリスマスという映画の内容を教えてください! |

出渕裕機動警察パトレイバー 6 1/2「かわら版」その2 
ビル・ヘイリーBill Haley(ビル・ヘイリー) 
伊藤左千夫伊藤左千夫『茶の湯の手帳』~オーディオ・ノベル・クラシック 
アマゾン河アマゾン川をカヌーで進む 
スペースインベーダーなつかしゲーム スペースインベーダー アーケード版 
フィリップ・ベイリービジーフォー アースウィンド&ファイヤー 宇宙のファンタジー 
MANDARINA DUCKPure Black by Mandarina Duck Fragrance/Cologne Review (2009) 
LOVERSKylie Minogue - All The Lovers |
[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
ピューマのクライミング Climbing of Puma.
平井堅 Ken Hirai - 輕閉雙眼 Hitomi wo tojite
乗換 あざみ野駅⇒東名江田バス停 Azamino Station⇒Toumei-Eda Bus Stop Transit
Consiglio comunale aperto su economia e commercio - 22 gennaio 2014
急上昇ワードを発音してみよう!『大木聖子』2012/09/11名倉右喬
戦場のメリークリスマス ウェブ
