
1964年1月2日から1965年11月18日までのべ10日間で録音。
新ウィーン学派の中心的存在アーノルド・シェーンベルグのピアノ作品集。12音階を用いた彼の作品についてはおそらく説明の必要はないだろう。
グールドがバッハを読み解くアプローチと同じアプローチでこのピアノ曲集に挑んだことは当然の事のように感じられる。そしてグールドはそのからくりを解く一歩手前まではこの中で行っていると思う。 しかし、この10年後ポリーニはその謎を全て解く演奏をして見せる。 シェーベルク没後100年の1974年5月ミュンヘンでポリーニにはこれらの曲集を録音する。10指の完璧なコントロールで解かれた12音階の構築物はそこでついに全てのカタチをみせてくれる。是非ともそちらも聴いて欲しい(●^o^●)。
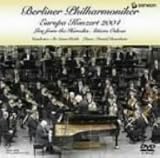
2004年のベルリン・フィルの創立記念日である5月1日に行われた「ヨーロッパ・コンサート2004」の模様を収録したDVD。 収録曲は:「ピアノ協奏曲第1番」(ブラームス作曲)とシェーンベルク編曲による「ピアノ四重奏曲(管弦楽版)」(ブラームス作曲)。
ピアノはバレンボイム。指揮はサイモン・ラトル。オーケストラはベルリン・フィル。 「ラトル&ベルリン・フィル」の演奏。期待が高まります。

坂本龍一が グールドを選んだアルバムである。これはもう聴くしかない。
坂本のバックグラウンドはクラシックであることは知られている。坂本のアルバムを聴くにつれて 時折 きちんとクラシックに還ってきている点は 音楽を聴く耳が弱い僕にしても聴き分けることができる事実だ。そんな坂本が 演奏者としてのグールドを選ぶという企画は楽しい。ましてや バッハを抜きにしてという 極めて野心的かつ実験的なアルバムである。この「バッハ抜きのグールド」というところに 坂本のケレンが見てとれる。
坂本はライナーで 最後に こう言っている。
「だから 今 グールドの後に演奏家になるってのは ほんとに大変なことだと思います
よ。でも みんな乗り越えてやってほしいとは思いますけどもね。やっぱりグールドの
ような演奏家はなかなか出てこないでしょうね」
演奏家としての坂本の視線が見えるような素直な発言だ。この言葉が 坂本が このアルバムを作るにおいての一番の動機だったのではなかったろうか?

ロサ三部作と呼ばれる「ロサ・シリウス」「ロサ・ギガンティア」「ロサ・クライシス」の3曲だけでも充分“買い”だが、「暁」「La Reine」も素晴らしい旋律。
「ロサ・ギガンティア」はLIVEでサビをみんなで大合唱したら最高だろう。
「ロサ・クライシス」はギターのイントロで拳が上がらないようではメタラーでは無いと言っても過言ではない、必聴のシンフォニック・スピード・メタル。
ネオクラシカル、シンフォニックメタル好きなら是非とも聴いてみるべき。

店舗で見かけなくなったのであきらめていましたが Amazon で見つかりました。
個人的には20年前のインバル・フランクフルト放送交響楽団の演奏が一番気にいってますがそういう観点ではこの演奏は盛り上がるところで急にペースダウンしてしまう点が最初は気になりました。
それでもにぎやかだし、うまくまとまっていると思います。
DVD で見ると大編成で楽団員の方が窮屈に演奏しているのがよくわかります。
因みに20年前のインバル・フランクフルト放送交響楽団の時の合唱団・合唱指揮者がこの演奏にも加わっています(時がたってますしドイツ統合の影響などで当時とはだいぶ違っているようですが)。
Andersen は最近のグレの歌の録音(ヴァルデマール役)でたびたび登場するようです。
第一部の最後に山鳩役の藤村さんが登場します。
ボーナストラックには「導入」がありますがドイツ語です。
初めて聞く方向けの簡単な解説をすると、これがシェーンベルク?と思ってしまうような曲想の歌曲です。
ヤコプセンの詩(「サボテンの花ひらく」)の中のデンマークのグレに伝わる実話に基づく伝説をドイツ語訳したものがベースになっています(現地ではこの伝説にもとづくお祭りもあるようです)。
シェーンベルクがツェムリンスキー指導下にあった初期の作品の一つで、10年以上かかりほぼ100年前(1911)に完成した作品です。
第一部・第二部のオーケストレーションはすぐに完成したため後期ロマン派のわかりやすい作風ですが、第三部のオーケストレーション(特に後半)は、完成の直前に手がけられ、後のシェーンベルク独特の作風が自然に入ってきています。
それで独特の曲想なのですが、シェーンベルクを苦手にしている方にも抵抗はなく受け入れられる、この時代を知ることができる作品と思います。
日本語の解説はありませんがそれでも無理なく受け入れられるでしょう。
一時期画家を目指していたらしく作曲に戻っても資金が底をついていたから10年以上かかったようです。
この商品のカバーはその時期(1910)にシェーンベルクによって書かれた絵「landschaft」らしいです。
| 
