
1974年12月、世間が「エマニエル夫人」公開を前にして騒がしかった師走のある日、東京有楽町の日劇文化に新作封切りのこの映画を見に行って、このパンフレットも買いました。値段は、たしか100円でした。当時は、映画のパンフレットはB5サイズで、値段は200円が一般的でしたが、これはA5サイズで、アートシアターのパンフレットに比べても紙質は悪いし、薄っぺらいし、ずいぶん配給会社から虐げられた映画なんだなあ、と思ったものです。
そもそも私にしても、べつに取り立ててこの映画が見たくて劇場まで足を運んだわけではありません。同時期に新作封切りされた「アマルコルド」だったかを見ようと丸の内ピカデリーに行ってみたところ、すでに上映期間が終っていたため、仕方なく有楽町界隈をぶらぶら歩いていてふと日劇文化の階段を下りてみると、やっていたのがたまたまこの映画で、開始時間がちょうど合ったので見てみた、というだけの話です。平日だったこともあって劇場はガラガラ(私を含めて3人いたかどうか)で、ちょっと不安を感じたほどです。クソつまらん映画だったらどうしよう、とか、変態に襲われたらどうしよう、とか。見始めたら、そんな不安は杞憂に終わりましたけど。
この映画も今ではポピュラーになりましたから、その魅力は皆様もよくご存じの通りですが、当時のタルコフスキーと云えば、「僕の村は戦場だった」一本のみで知られている人で、しかもそれが公開されてから10年間も経過していたこともあって、完全に忘れられた、過去の人でした。彼が今の様に巨匠扱いされるようになったのは、1987年に遺作の「サクリファイス」が公開され、アカデミズムの権威筋がやたらに持ち上げてからのことではないでしょうか。
このパンフレットは現在どなたも出品されてはいないようですが、当時それほどポピュラーな映画ではなかったために所有している人が限られるであろうこと、紙質が悪くて長期間の保存に適さないであろうこと、などから、希少品だとは思います。相当な値がつくことでしょう。私が所有しているものは、数十年間、厳重に保管してきましたので、しわ折れなどまったくありません。もちろん手放す気もありませんが。

1974年の暮れの事であった。新聞の映画広告欄に、奇妙な映画の広告が有るのに、私は、気が付いた。それは、余り目立たない、小さな広告で、その映画の一場面らしい、黒衣に身を包んだ僧侶の姿と共に、「当分御覧になれません。この機会をお逃しなく!」とか、そんな言葉が書かれた、細長い、短冊の様な広告であった。
当時、私は、高校生であった。何故か、その広告が気に成った私は、その映画は、一体どんな映画なのだろう?と思ひ、その気に成る映画を観に、今は無い、有楽町の日劇の横に有った小さな映画館へと向かった。そして、そこで観たその映画こそは、今日まで、私の人生で最良の映画であり続けるこの作品(『アンドレイ・ルブリョフ』)だったのである。
ロシア中世のイコン(聖像)画家であったアンドレイ・ルブリョフを主人公とするこの映画は、旧ソ連が、巨費を投じて製作しながら、完成後、ソ連国内では、事実上上映禁止と成った「問題作」であるが、そんな事は、最早、どうでも良い事である。
私は、この映画は、世界映画史上最高の作品であると思ふ。この映画を見ずに、映画と言ふ芸術を語っては成らないと、私は、思ふ。
タルコフスキーは、日本映画に深く傾倒して居たと言ふ。新しい映画を作る前には、黒澤明の『七人の侍』と溝口健二の『雨月物語』を必ずもう一度見直すことにして居たと言ふ彼についての逸話は、興味深い。(タルコフスキーを観る若い人は、この事を知って欲しい)実際、この映画には、『七人の侍』と『雨月物語』を思ひ出させる部分が少なくない。(逆に、タルコフスキーの作品を深く愛した日本の作曲家、武満徹氏が、タルコフスキーの死を悼んで、弦楽合奏曲「ノスタルジア」を作曲した事も、日本の若い人は、知って欲しい。)
深く、静かな、美しい作品である。私は、この映画に出会えた事を、神に感謝して居る。
(西岡昌紀・内科医/タルコフスキーの誕生日に)
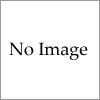
−−伊勢丹前の新宿文化劇場で『アンドレイ・ルブリョフ』を見たのは一九七四年(昭和四十九)年十二月八日でした。戦中派の私にとっては、日本がハワイ真珠湾の空襲を開始した日に当たっていたことと、翌日、田中内閣に代わる三木武夫内閣が成立したことで記憶に残っているのです。ああ、もう二〇年もたったのかと、おどろきを禁じえません。(本書273ページ「あとがき」より)−−
本書の著者落合東朗(おちあいはるろう)氏は、1926年北海道に生まれ、1945年7月、満州のハルビンで関東軍に入隊、シベリアに抑留された後、帰国して早稲田大学でロシア文学を専攻した著述家である。氏は、ロシア正教に関心を持ち、ロシアのイコン(聖像画)に魅了されて居たと、本書の「あとがき」に有る。本書は、その落合氏が、タルコフスキーの傑作『アンドレイ・ルブリョフ』(1966年)の内容をシナリオに照らして検証しながら、当時のソ連の体制から考えれば驚くべき内容の作品であったこの傑作が撮影、製作された際の舞台裏を述べ、検証した研究書である。
本書を読んで興味深かった事の一つは、『アンドレイ・ルブリョフ』が撮影、製作されるに至った背景に、文芸界の自由派を批判した事で知られるイリイチョフ氏が、この作品の撮影にゴーサインを出した張本人だったと言ふ逸話であった。(本書93−94ページ参照)『アンドレイ・ルブリョフ』の中の科白通り、「ロシアは不思議の国」である事を痛感した。
(西岡昌紀・内科医/タルコフスキーの命日に)

この映画は、ロシア中世の聖像画家アンドレイ・ルブリョフの半生を、想像の物語として描いた作品である。監督のアンドレイ・タルコフスキーは、詩人アルセニー・タルコフスキーの息子で、日本文化に深く傾倒して居た事で知られて居る。
旧ソ連は、巨費を投じてこの映画をタルコフスキーに製作させたが、完成した映画の内容は、その反体制的な内容からソ連当局の怒りを買ひ、1966年の完成後、ソ連国内では事実上上映禁止の状況に置かれる事と成った。その『アンドレイ・ルブリョフ』が、西側で知られる事と成ったのは、当時のフランスの文化大臣アンドレ・マルローが、この作品がカンヌ映画祭で上映される様尽力した事が大きいと言はれて居る。
1974年、この言わくつきの映画が日本で公開された時、私は、これを東京の映画館で観る幸運を得た。以来、今日に至るまで、この映画は、私の人生最良の映画である。−−あの鐘造りの若者の物語と、その後にヴャチェスラフ・オフチンニコフの音楽と共に画面に現れるルブリョフのイコンには、何度見ても感動を禁じ得ない。一枚の絵の陰に、歴史に埋もれた人々の悲劇と苦難が有った事を、この映画の末尾の部分は教えてくれる。−−私は、この映画は、世界映画史上最高の作品であると思ふ。この映画に出会へて、私は幸福であった。
(西岡昌紀・内科医/タルコフスキー没後20年目の日(2006年12月29日)に)
| 

